北信五岳のひとつである戸隠山は、古くから山岳修験の山として知られています。日本二百名山にも数えられ、標高は1904メートル。長野県長野市にある戸隠神社奥社から登るルートが一般的です。岩場とクサリ場が連続する箇所も通るので、非常にスリリングな山行となります。
戸隠神社奥社から周回でで戸隠山に日帰り登山した様子を記していきます。
↓ YouTubeにも動画を上げています。動画も見てもらえると雰囲気がイメージしやすいので、よかったらどうぞ。
ルート概要
【標準コースタイム】
登り 4時間15分
- 高妻山登山者用駐車場から「さかさ川遊歩道」を歩いて戸隠神社奥社入口へ
- 戸隠神社奥社入口からスギ並木を歩いて戸隠神社奥社近くの戸隠山登山口へ
- 戸隠山登山口から戸隠山山頂へ
下り 3時間54分
- 戸隠山山頂から九頭竜山を経由して一不動へ
- 一不動から戸隠キャンプ場へ
- 戸隠キャンプ場から高妻山登山者用駐車場へ
【日 程】
2020年8月29日(土曜日)
戸隠山の山行記録
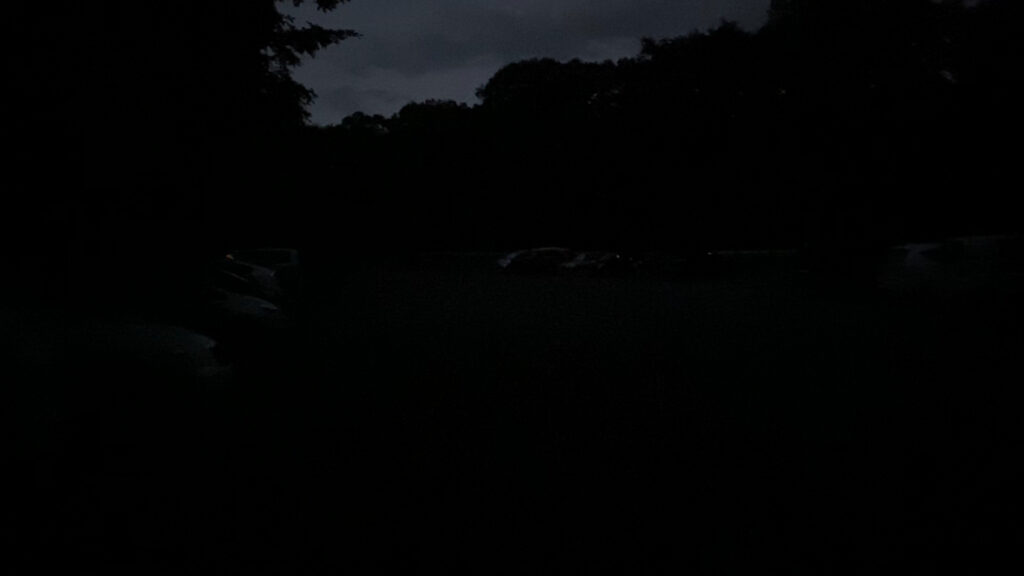
朝4時45分、戸隠キャンプ場近くの高妻山登山者用駐車場。まだ暗い時間ですが、駐車場は5割ほど埋まっていました。トイレは道路を挟んで向かい側にあります。

ちなみに9時00分の時点でほぼ満車でした。(下山時に撮影)

さかさ川遊歩道を通って戸隠神社奥社入口まで行きます。

まだ暗いのでヘッドライトの灯りが頼りです。

戸隠神社奥社入口。大きな鳥居をくぐり、一直線の参道を進みます。

参道の真ん中くらいにある随神門をくぐる。

随神門を過ぎると樹齢400年を超えると言われている杉並木を歩きます。少し進むと左側にトイレがあり。戸隠神社奥社手前の道は石の階段歩きです。

戸隠神社奥社に着いたら社務所の脇を通って登山口へ。

戸隠山の登山口。登山届の用紙とポストあり。

いきなり急登が始まるので、息を整えながらマイペースで進むことが大切です。尾根に近づくにつれて大きな岩が連続して見えるようになります。

岩壁の下部が長くえぐれた五十間長屋。

岩壁に沿って歩くとその高さに圧倒されます。

百間長屋通る。五十間長屋と同様に岩壁の下部がくりぬかれたような形状をしています。

石の祠が祀られている西窟。

通過してきた岸壁を振り返る。垂直を超えて登山道側に岸壁が傾いて見え、とんでもない所を歩いてきたのだという気分になります。

西窟を過ぎて少し進んだ辺りから蟻の塔渡りまで、クサリ場が延々と続くようになります。

ずっとクサリ場を進む緊張を強いられるので、たまに遠くの景色を見て一休み。

胸突岩では、ほぼ垂直な岩を直登します。

クサリを頼りに慎重に少しずつ進む。

このコース最大の難所である蟻の塔渡りに着きました。過去に滑落事故が何度も起きていることで有名な怖い所です。

左右が切れ落ちているため、非常に高度感があります。

立って歩く勇気がなかったので、四つんばいになって進みました。

青い花のリンドウ。

見通しのよい八方睨に到着。この場所が戸隠山山頂っぽいですが、もう少し先にあります。

同じ戸隠連峰の山である高妻山がよく見えました。

八方睨の分岐を右に進めば戸隠山山頂です。間違っても左の西岳方面には行かないようにしましょう。

先ほど通過した蟻の塔渡り。高い位置から見ると違った印象を受けます。

戸隠山の山頂。ある程度展望はありますが、こじんまりとした所に山頂標識が1本立っているだけです。

大きな難所は越えましたが油断はできません。右側が崖になっている所もあるので注意です。

九頭竜山を通過。ここから一不動まで登り下りがあります。

ようやく見えた一不動の避難小屋。

一不動には高妻山方面と戸隠牧場方面との分岐があります。分岐を右に進んで戸隠牧場方面へ。一不動から戸隠牧場までのルートは沢を下るような箇所もあるので、夏は涼しげな雰囲気です。

途中、氷清水と呼ばれる水場があります。

猛毒のトリカブト。

帯岩と呼ばれる岩の斜面を横切ってから岩場を下ります。足場は切ってありますが、ぬれていると滑るので足元注意。

沢状の道をどんどん下ると樹林帯に入ります。

樹林帯が終わった先が戸隠牧場です。

戸隠牧場の道を歩いて戸隠キャンプ場へ。

戸隠キャンプ場をまでくればゴールである高妻山登山者用駐車場はもうすぐです。

高妻山登山者用駐車場に到着。8月の登山シーズン真っただ中なので、車の数もすごかったです。
今回の戸隠山周回は、戸隠神社奥社の参道に始まり、岩場・クサリ場、沢下りと色々変化に富んでいて飽きないです。もし登る際は、滑落と隣り合わせの危険な山であることを念頭に置いて、スリリングな山行をお楽しみください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。









